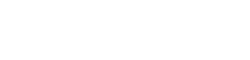七五三にはかかせない紅白の長~い千歳飴。
着物姿の小さな子どもが大きな千歳飴の袋を手にした光景はとても微笑ましいですよね。
この千歳飴、子どもにはちょっと長すぎると思うのですが、短く折ってもよいのでしょうか?
正しい食べ方はあるのか、残った千歳飴はどうすればよいのか。千歳飴の由来や起源、長さや袋のデザインの意味もあわせてご紹介します。
七五三の千歳飴
七五三は、子どもの健康と長寿を願う日本の行事。
男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳に、お寺や神社にお参りしてご祈祷してもらいます。
そのご祈祷のあとにいただくのが千歳飴。
松竹梅や鶴亀が描かれた袋のなかに、白とピンク色の長い飴が入っていますよね。
今日は11月15日(旧暦10月8日)の木曜日
「七五三(しちごさん)」
3歳、5歳、7歳の節目に、子どもの成長を願って、
縁起のよい千歳飴を買い、氏神様へお参りします。暦生活https://t.co/OPnU64fISu #暦生活 #七五三 #季節 #カレンダー #暦生活 #新日本カレンダー pic.twitter.com/JOv5TUaZJV
— 暦生活 (@543life) November 14, 2018
おもな原料は水飴と砂糖で、太さは直径14.5㎝以内、長さは1m以内と決まっているそう。
子どものころは「なんでこんなに長いんだろう」と不思議に思っていたけれど、この長さには、子どもへの長寿の願いが込められています。
千歳飴を折るのはOK?
子どもの成長を祈願する縁起物の千歳飴。
長生きするようにという願いが込められた千歳飴ですが、子どもにとってはちょっと食べにくいですし、途中で飽きてしまいがちですよね。
めいっこが食べかけて途中で飽きた千歳飴を、私ももらったことがあります。笑
そのとき、私はすぐに小さく砕いてしまったのですが、ご祈祷していただいた千歳飴を折ったり切ったりしてもよいのでしょうか。
千歳飴の正しい食べ方は?
ご祈祷やお祓いをうけた千歳飴を折ったり切ったりして食べるのは縁起がわるいのでは?と不安に思われるかもしれませんが、千歳飴には特に決まった食べ方はありません。
それに、小さな子どもに長~い千歳飴をそのまま食べさせるのは危なくて心配ですし、虫歯やカロリーも気になりますよね。
千歳飴を食べる風習が広まった江戸時代、砂糖はとても貴重なもので、千歳飴は家族みんなで大切に食べていたと言われています。また、地域によっては「お福分け」として親戚やご近所に配る風習もあります。
なので、千歳飴は折ったり切ったり砕いて食べても問題はありませんし、千歳飴の正しい食べ方というものもありません。
千歳飴は本来、子どもの健康と長生きを願い、みんなで食べていたもの。子どもの健やかな成長を願って七五三をお祝いし、ご家族みんなで食べてみてはいかがでしょうか。
千歳飴の折り方・切り方
ご祈祷やお祓いを受けた縁起物の千歳飴。
長いまま食べて、途中で飽きて残したり、捨ててしまうのはもったいないですよね。
もちろんそのまま食べてもよいですが、余りそうなら小さく分けておくのがおすすめです。
千歳飴を小さく折るときは、袋に入れてすりこ木などで叩いて砕きます。ただし、このやり方だと尖った形になることもあるので、食べるときには十分注意してくださいね。
また、切るときはキッチンバサミや包丁を使いますが、そのままだと結構硬いので、電子レンジで温めてやわらかくしてから切ると切りやすくなります。飴はすぐに溶けてしまうので、様子を見ながら数秒ずつ加熱してみてください。

子どもの長寿の願いが込められた千歳飴は、食べきることに意味があると思います。
千歳飴を小さく切っても食べきれない場合は、料理や飲み物、お菓子作りの砂糖の代わりとして使うこともできるんですよ。
残った千歳飴のアレンジレシピ
小さく切っても残ってしまった千歳飴。
砂糖の代わりに、料理や飲み物に入れたり、お菓子作りに使って活用しましょう。
おすすめアレンジレシピをご紹介しますね。

出典:cookpad
甘みに、砂糖+千歳飴を使った卵プリンです。
スが入らないように、極弱火で蒸していきます。
![]() 簡単おやつ☆千歳飴リメイク☆ミルクプリン by いのししベーカリー
簡単おやつ☆千歳飴リメイク☆ミルクプリン by いのししベーカリー

出典:cookpad
こちらのプリンは、甘みは千歳飴だけ。
ゼラチンで固めるレシピなので、とても簡単です。
ゼラチンを加える前に、温めた牛乳に砕いた千歳飴を入れて溶かしていきますが、あま~いホットミルクとして飲んでもおいしいですよ。
![]() 材料3つ!炊飯器×千歳飴で超簡単☆大学芋 by keikana
材料3つ!炊飯器×千歳飴で超簡単☆大学芋 by keikana

出典:cookpad
七五三のある秋は、さつまいものおいしい季節。
こちらは、炊飯器で作る大学芋のレシピです。
味つけは、千歳飴としょうゆだけです。
![]() 千歳飴deしっとりソフトクッキー♡ by renanatsu
千歳飴deしっとりソフトクッキー♡ by renanatsu

出典:cookpad
クッキー生地の砂糖を千歳飴で代用したレシピ。
バターと牛乳、千歳飴を弱火で溶かしていきます。
ふんわりサクサクでおいしそうです♪

出典:cookpad
千歳飴を照り焼きダレに活用するレシピです。
香りや色つきの飴でも、煮つめていくことで違和感なくいただけるそうですよ。
照り焼きだけでなく、煮物に使ってもよいですね。
このように工夫して、残った千歳飴をお菓子作りや飲み物、料理に活用することで、無駄なく食べきることができます。気になるレシピがありましたら、ぜひおためしください。
千歳飴の由来と起源
千歳の飴というおめでたい名前のついた千歳飴。
千歳とは千年を表し、千年も長く、つまり長生きしてほしいという意味が込められています。
七五三が庶民に広く広まったのは江戸時代。
5代将軍の徳川綱吉が、長男(徳川徳松)の健康を祈ったのがはじまりと言われています。
また、千歳飴の起源は諸説ありますが、いずれも江戸時代がはじまりとされています。
ひとつは、江戸時代の元禄年間、浅草寺の境内で、飴売りの七兵衛が紅白の棒状の飴「千年飴」を売りはじめたという説。また一説には、同じころ、大阪から江戸に出てきた飴屋「平野屋」の平野甚左衛門が、浅草寺の境内で「千歳飴(せんざいあめ)」を売りはじめたと言われています。

千年飴と千歳飴。どちらも「長い千歳飴を食べれば千年の長寿になる」として売り出された飴は、七五三参りの定番のお土産として人気がでて、江戸の庶民に広まっていきました。
いまとは違い、むかしは大人に成長することが当たり前ではなく、流行り病などで早世する子どもがたくさんいました。わが子の健康や長寿を願う想いはとても切実なもので、そんな願いから生まれたのが千歳飴だったのです。
千歳飴の長さや袋に込められた意味
千歳飴が長いのは、健康で長生きできるように。
千歳飴には、子どもの健やかな成長と、長寿を祈る気持ちが込められているのですね。
また、飴の長さだけではなく、千歳飴が入った袋にも意味が込められているんです。
神社でのご祈祷のあと、お土産でいただく千歳飴。
その袋には、松竹梅や鶴亀、寿など、とてもおめでたい絵や文字が描かれています。
11月は七五三。晴れ着と共に「千歳飴」が欠かせませんよね。 誰もが知っている通り細長い棒状の飴ですが、どのように始まり、どんな願いが込められているのでしょうか。https://t.co/bxbGlPRWor pic.twitter.com/tAwLrzN4qd
— ウェザーニュース (@wni_jp) November 11, 2018
そして、袋のなかには細長い紅白の飴。
それぞれどのような意味があるのでしょうか。
fa-check-circle紅白の色・・・縁起が良い色
fa-check-circle鶴と亀 ・・・長寿の象徴
fa-check-circle松竹梅 ・・・健康と力強さを願う気持ち
fa-check-circle寿の文字・・・おめでたいという意味
鶴は千年、亀は万年という通り、鶴と亀には長生きの意味があり、長寿の象徴です。
そして、冬の寒さのなかでも緑を絶やさない松と竹と、越冬してすぐに花を咲かせる梅。
松と竹、梅の力強く健やかに生長するさまから、松竹梅には、健康で強く生きてほしいという願いが込められています。
小さな子どもにはちょっぴり持ちにくい千歳飴。
長い飴の形には意味があり、紅白の色や袋のデザインまで、子どもの健やかな成長を喜びお祝いする気持ちと、千歳飴のように長く生きてほしいという願いがつまっているのですね。
おわりに
親から子どもへの深い想いが込められた千歳飴。
ご祈祷を受けた縁起物ですが、折って食べるのは問題ないですし、正しい食べ方というものもありません。自分にあった食べ方でありがたくいただきましょう。
千歳飴は、食べきることに意味があります。
小さく分けて家族でおいしくいただいたり、それでも食べきれない場合は、料理や飲み物、お菓子作りの砂糖の代わりとして使ってみるのはいかがでしょうか。
紅白で長い形、そして袋にも意味のある千歳飴。
これまで成長してくれたお祝いと、これからの健康と長寿を祈願する千歳飴を食べて、心にのこる素敵な七五三となりますように♪