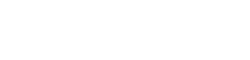巻きずしの具としてよく使われる干瓢(かんぴょう)
かんぴょうって何から作られているかご存じですか?
朝顔でもなく、昼顔でも夜顔でもなく・・・
かんぴょうがどんな野菜から作られているのか、気になる作り方や栄養価もご紹介します。
かんぴょうの原料は何の瓜?
白いひも状の乾物として販売されているかんぴょう。
かんぴょうの原料って何だと思いますか。
かんぴょうの原料は、ユウガオという野菜なんです。
きれいな花も咲かせるユウガオは、ウリのなかま。
ウリ科ユウガオ属の一年草です。
7月から9月に大きな瓜のような実をつけ、それをむいて干したものがかんぴょうです。
【滋賀県】
特産物:水口かんぴょう
甲賀市水口が産地となっていることから、"水口かんぴょう"と言うそうです😊
手巻き寿司の具としてよく活躍していますよね✨
元々は"ユウガオ"という実からできるそうです🍐#滋賀県#滋賀#水口かんぴょう pic.twitter.com/UvyW9vh4Ij
— とくさん (@tokutokujapan33) 2018年11月19日
ユウガオには、長い円筒状になる品種もありますが
かんぴょうに加工されるのは、おもにマルユウガオ。
かんぴょうは、漢字では干瓢と書きます。
瓢は「ふくべ・ひさご」と読み、ひょうたんのこと。
ふくべはユウガオの実のことで、ひさごは、ひょうたん・ユウガオ・冬瓜などの総称です。
ウリ科の冬瓜も、ユウガオのなかま。
属は違いますが、ユウガオと同じ時期の7月から9月に収穫される夏野菜です。
かんぴょうの作り方は?
ユウガオの実が原料のかんぴょうですが
どのようにして作られているのでしょうか。
まず、ユウガオの緑色の皮を厚くむき、白い実の部分をひも状にむきます。それを重ならないように干して、乾燥させたらできあがり。
機械でむく場合は、ろくろのような専用のむき機にかけ、実を回転させながら、帯状に長くむいていきます。厚さを一定にむくのには、長年の経験と熟練の技が必要です。
人気の
かんぴょう剥き動画をあげると
楽しそう!やってみたい!とよく言われます見てると簡単そうですが
ユウガオの実からの反動を抑えつつ長く均一に剥くのはコツがいりますそして100個以上の実をひたすらむきます#かんぴょう剥き #地味作業 pic.twitter.com/HU6dKzhx8o
— かんぴょう問屋マルモ (@chibi_marumo) 2019年2月19日
ひとつ6キロから8キロもあるユウガオの実からは、150~200gの原料しかとれないのだそう。
また、早朝の新鮮な実でなければ皮が硬くなってきちんとむけないため、収穫はまだ暗いうちからはじまります。むいてから乾燥させるあいだも手間がかかり、雨よけや、甘いかんぴょうに虫がよらないようにするなど、かんぴょう作りはとても大変な作業です。
かんぴょうの栄養価
巻き寿司にはかかせないかんぴょう。
甘辛く煮つけると、味がしみておいしいですよね。
栄養価についてはあまり知られていませんが、かんぴょうは栄養たっぷりの食品なんです。
かんぴょうは、食物繊維が豊富なのが特徴。
100g中当たりでは、ごぼうの約4倍と切り干し大根よりも多く含まれ、カルシウム・カリウム・リン・鉄などのミネラルもとても豊富です。

また、一般的な白く漂白されたかんぴょうのほか、飴色をした無漂白のものもあります。
漂白は、防カビ・防虫や変色防止のために、二酸化硫黄で燻しておこないますが、水溶性の二酸化硫黄は水に溶けやすく、調理前に水洗いすれば流れ落ちるので害はありません。
無漂白かんぴょうは少数生産ですが、自然な甘みがあり、早く柔らかくなります。もどし汁にはうま味と栄養が多くあり、かんぴょう本来の風味は格別です。
おわりに
かんぴょうの原料は、ユウガオの実をむいたもの。
作り方も、収穫から加工まで手間がかかるもので、とても大変な作業なんですね。
ちなみに、ウリ科のユウガオと名前がよく似ている朝顔・昼顔・夜顔はヒルガオ科。ユウガオとは分類が異なり、大きな実をつけるのはユウガオだけです。
かんぴょうは、ミネラル豊富で、特に食物繊維がとても多く含まれています。脇役になりがちなかんぴょうだけど、これからは栄養成分にも注目して食べたいなと思います。