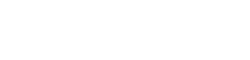南のほうから、梅雨の足音が聞こえてきましたね。
雨の名前には、菜種梅雨やたけのこ梅雨のように、植物の名前がついたものが多くあります。
卯の花腐し(くたし)も雨の呼び名なのでしょうか?
今回は、梅雨シーズンの雨を表すいろいろな雨の名前をご紹介していきます。
卯の花腐しとはどんな意味?
サクラや菜の花が咲くころに降り続く菜種梅雨。
たけのこが生えるころの長雨をたけのこ梅雨。
春から夏にかけての雨は、植物が生長するための大切な雨であることから、このように植物の名前がついた雨の呼び名が多くあります。
菜種梅雨は、3月中旬から4月にかけて降る雨。同じ意味を表す雨に、催花雨もあります。
桜が終わり、春の雨の時期を過ぎると、季節は初夏。
5月初旬のたけのこ梅雨を経て、卯の花腐し(うのはなくたし)の雨へと移っていきます。 卯の花腐しは、雨の呼び名なんですね。

卯の花は、ウツギという花の別名。
食べ物のおからではなく、花のほうの卯の花です。
多くの種類があるウツギは、昔から愛されてきた花。
万葉集には、 卯の花を詠んだ歌が24首登場します。
さて。腐す(くたす)とは、腐らせるとか、朽ちさせる、だめにするという意味。
うのはなくだし、とも読まれます。
卯の花腐しは、読んで字のごとくウツギの花を腐らせるという意味なのですが、それでは卯の花腐しとはどんな雨のこと表すのでしょうか?
卯の花腐しとはどんな雨のこと?
卯の花は、ユキノシタ科ウツギ属の落葉低木。
5月中旬から6月に白い花を咲かせる初夏の花です。
卯の花腐しは、卯の花の咲く5月中旬から6月上旬に、数日間降る雨のことを言います。
ウツギの花がきれいに咲くこの期間に、花を散らして朽ちさせるほど降り続く雨。走り梅雨とも言われますが、卯の花腐しという呼び名には情趣を感じます。
また、卯の花が咲くころの曇り空は卯の花曇り(うのはなぐもり)と言われます。
こちらも素敵な言葉ですね。
卯の花腐しは、本格的な梅雨の前触れ。
すこしずつ梅雨の足音が近づいてきています。
梅雨シーズンの雨の名前
日本には、四季を通じて、雨を表す言葉がたくさんあります。これは日本ならではの文化。
梅雨の季節には、卯の花腐しのほかにもたくさんの雨の名前があるんですよ。
fa-umbrella走り梅雨(はりしづゆ)
5月中旬から6月上旬にかけて降り続く雨。
卯の花腐しと同じ、梅雨入り前の雨のことです。
迎え梅雨(むかえづゆ)とも言います。
fa-umbrella入梅(にゅうばい)
梅雨入りのこと。
梅の実が熟すころに降る雨が由来となっています。
fa-umbrella栗花落(ついり)・堕栗花(ついり)
梅雨入りのこと。
栗の花が散るころに降る雨が由来です。
fa-umbrella五月雨(さみだれ)
梅雨のこと。
旧暦の5月ごろに降る長雨です。
fa-umbrella麦雨(ばくう)
麦の熟するころに降る雨。
梅雨や五月雨の別名です。
fa-umbrella送り梅雨(おくりづゆ)
梅雨が明けるころの雨。
雷を伴うことが多く、集中豪雨になることも。
fa-umbrella戻り梅雨・返り梅雨・残り梅雨
梅雨が明けて、再び雨が降り続くこと。
fa-umbrella空梅雨(からつゆ)・枯れ梅雨(かれつゆ)
雨があまり降らない梅雨のこと。
早梅雨(ひでりつゆ)とも呼ばれます。
fa-umbrella荒梅雨(あらつゆ・あれつゆ)
梅雨の後期に、
災害をもたらすほどの集中豪雨となること。
fa-umbrella暴れ梅雨(あばれづゆ)
梅雨の終わりごろに強い雨が続くこと。
fa-umbrella男梅雨(おとこづゆ)
激しく降ってはさっと止み、すっきり晴れる梅雨。
陽性梅雨(ようせいばいう)とも。
fa-umbrella女梅雨(おんなづゆ)
弱い雨がしとしと降り続く梅雨のこと。
陰性梅雨(いんせいばいう)とも言います。
fa-umbrella出梅(しゅつばい)
梅雨明け。梅雨が終わる日のことです。
おわりに
卯の花腐しとは、卯の花(=ウツギ)の咲くころに降り続く長雨のことなんですね。
菜種梅雨からたけのこ梅雨、そして卯の花腐しへと季節は移ろい、いよいよ梅雨入りへ。
卯の花腐しは夏の季語でもあり、すこし気の早い夏の訪れを感じさせてくれるようです。